形容し難い危ない
麻薬的魅力を放つ「映画」だ。
芥川賞作家・中村文則による原作、今や注目度No.1の俳優・瀧内公美の卓越した演技力、そのふたりの才能の参加を得て映画界に半世紀近く携わる奥山和由が常識を覆す演出方法で仕上げた。
この映画、観客は観終わってもしばらくの間、美しい映像や劇中のサブリミナル音に支配される。そして耳に残る印象的なピエロの口笛。きっと多くの人は映画から解放された後、いつの間にかそのメロディーを口ずさんでしまうだろう。女の語る半生は人の道を踏み外した悲惨な話でありながら、どこか心地良さすら感じてしまうのだ。そして、気がつくと自分に何が起こっても大したことではない、いずれ少しは幸せになれるはずという気がしてしまう。それは理屈抜きの映画的マジックだろうか。
スタッフは『RAMPO』以来約30年ぶりに監督を務めた奥山和由のもとに、「鎌倉殿の13人」などの撮影監督・戸田義久、美術の名匠・部谷京子、『ミッドナイトスワン』などの録音・伊藤裕規、『PERFECT DAYS』などの音響効果・大塚智子 等、日本映画を代表するスタッフが集結。それに加え、衣装のミハイル ギニス アオヤマ(ギリシャ)をはじめ、編集・陳詩婷(台湾)、ヘアメイク・董氷(中国)と国際色豊かなチームとなっている。
また、精神科医と主人公の関係の象徴の如き大きな絵画が冒頭から最後まで印象的に映り込んでいる。描く画家が絵に収まってしまい、それを逆に見つめる裸婦という逆転の構図。これは「真実」という標題の後藤又兵衛の原画である。後藤は日本では不遇の画家だったが、それに比して海外では圧倒的に高い評価を得ており、彼の絵の熱心なコレクターとしてハリー・ベラフォンテ、エルヴィス・プレスリー、フランク・シナトラなど歴史に名を残す錚々たるアーティスト達が名前を連ねている。
そして、全編を彩るピエロの口笛のメロディーは芸術文化功労賞受賞者であり国際口笛大会(IWC)での優勝歴を持つ加藤万里奈が担当した。
一流のスタッフ、アーティストによって生まれた、かつてない実験的な自主映画、そういう不思議な映画だ。 百聞は一見にしかず、としか表現のしようがない、本当に困った映画だ。





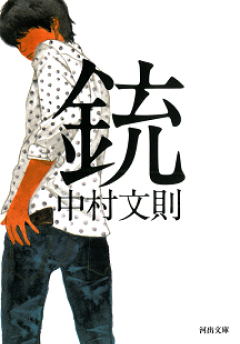






コメントを読む
この『奇麗な、悪』の原作の「火」は、様々な人から、演じてみたい、という声を聞いていた。
『火 Hee』として桃井かおりさん監督・脚本・主演で映画化され、「業火」として三木美智代さんによって舞台化されている。「火 Hee」でプロデューサーを務めた奥山和由さんから、「火」をもう一度映画にしたいと言われた時は、しかし驚いた。映画化としては、二回目になるから。
出来上がったものを観て、さらに驚くことになる。原作の通りではあるけど、これは一人の女性が、話しているだけの映画。なのに、これほどまでに、引き込まれる。
主演の、というか、お一人しか出演していないのだが、瀧内さんは実に見事だった。多方面から大きな注目を浴びている俳優とは知っていたが、従来の映画には見られない、ここでしか味わえない独特の言語空間をつくり出していた。一人の女性が、自分の内面の奥の奥を、誰もいない場所で、独白する。通常の言葉だけが、連なるはずがない。他者に言う自然な言葉もあれば、反対に内面の奥を探るような、社会化されていない観念的な言葉もある。そして構える言葉、吐き出す言葉、攻撃、防御、揺れ――、あらゆる種類の言葉が解き放たれ、映画空間に言葉の「場」がつくり出されていた。その演技力、存在感。すさまじかった。
映画は、小説よりもどこか「前」を向いている印象がある。瀧内さんによる、奥に芯の見える主人公像もそうだった。この映画はこのように完成したことで、「火」の主人公を救ったのかもしれない。
あらゆる文化が平均化していく中で、このような作品が日本映画にあることが、嬉しい。